ジェスロ・タル『天井桟敷の吟遊詩人』は英国伝統フォークとへヴィー・ロックの華麗な癒合

今晩は。ヴァーチャル・パブきつね亭です。
今日の演目はジェスロ・タルの『天井桟敷の吟遊詩人(Minstrel in the Gallery)』というアルバムでいきたいと思います。
1975年にリリースされたジェスロ・タル(通称タル)の9枚目のアルバムで、作詞作曲、ヴォーカル、フルート、アコギを手掛けるバンドのフロントマン、イアン・アンダーソンを中心に、ギターのマーティン・バー、キーボードのジョン・エヴァン、ドラムのジェフリー・ハモンド・ハモンドが参加しています。
このアルバムには、やはりイングリッシュ・エールそれもブラウン・エールをお勧めしたいと思います。
天井桟敷の吟遊詩人(Minstrel in the Gallery)
第1曲目の表題作。
天井桟敷というと通常階上の客席のことらしいですが、このギャラリーではジャケのイラストのように演じる側が陣取っています。
演者の口上に続き、パチパチとまばらな拍手。続いてアコギとフルートの調べに乗せて中世の吟遊詩人を思わせる節まわし。
面白いことに見る側と見られる側が反転して、吟遊詩人からみた客席の様子が語られています。おしゃべりに興じる老人からカボチャを食べる人、イカサマを働いた工場労働者、オムツが濡れてグズっている赤ん坊、新聞の日曜版のバックギャモンに取組む人、TVのドキュメンタリー制作者にいたるまで、次から次へと脚韻を踏みながら混沌とした世間の縮図が展開していくあたり作詞者としてのアンダーソンのセンスが窺われます。
曲はアコースティックな英国フォーク調から一転して中盤からヘヴィー・ロックの様相を呈します。変拍子の集積を潜り抜け、リズム・セクションが重厚な4拍子を刻み始めると、エレキ・ギターの絶妙なソロ。所々にフルートが絡みます。マーティン・バーはギタリストとして著名とは言い難いものの相当な実力の持主であることが窺い知れます。
ヴァルハラへの冷たい風(Cold WInd to Valhalla)
第2曲目はアルバムの中でも人気の高い曲です。
ヴァルハラは北欧神話の神が住む神殿、死んだ戦士をヴァルハラに誘なう妖女達がワグナーの楽曲でも有名なワルキューレですね。
英国風のフォークからハード・ロックに転じるというタルの曲の一つのパターンを蹈襲しています。
この曲は特に後半のギター・ソロが絶品。ストリングスの入れ方も効果的で、全体的に散りばめられたフルートは風に混じって聞こえるワルキューレ達の叫びのようです。
黒衣の踊り子(Black Satin Dancer)
個人的にはヴァルハラと並んで好きな曲です。
重厚なベースと華麗なフルートの音に導かれ始まるこの曲、こぼれるような可憐なピアノ、美麗なストリングス。いつの間にかワルツのリズムに。徐々にワルツのテンポが増してロックに突入。そしてマーティン・バーのギタープレイ。本当にこのギタリストはもっと知られていいと思います。
フルートがロックの楽器としてソロを張っているのもタルならでしょう。ドラムのシンバル使いも好きです。
レクイエム(Requiem)
アコギ、フルート、ウッドベース、甘やかなヴォーカルによる美しい、美しすぎる曲。
そして残酷な歌詞。微妙に背筋が凍ります。
一羽の白いアヒル/0の10乗=無(One White Duck/010ーNothing at all)
難解なタイトルに難解な歌詞で、イアン・アンダーソン自身が内面と向き合って描いているように思われます。ボブ・ディランのように弾き語っていて、個人的に好き・嫌いの範疇ではありません。ストリングスが美しい。ヴァイオリンのピチカート部分も。

ベイカー・ストリートの女神
17分近い作品。聴き終わって思わず溜息が出ます。
うまいのです。イアン・アンダーソンのヴォーカルが。多少の間奏を挟んで、延々とモノローグのように歌っているのですが、何というか達者としか言いようがありません。
FeelとかHeelのように脚韻を踏んで伸ばしているパートなど、もうクセになりそうです。
主旋律は英国のフォーク調で、中世のイギリスの村景色に似合いそうですなのですが、舞台はロンドンのベイカー街。決っして綺麗とは言い難い街路の様子がが描かれています。
(私事ですがロンドンに住んでいた頃は、ベイカー・ストリートは徒歩距離だったので、ベイカーとかメリルボーンとかいう地名が出てくるだけで、懐かしさで心臓が高なります)
この歌のテーマについては、イアン・アンダーソンが言明していないらしく、ネットでも「これは貧困層の悲哀を歌った政治的メッセージだ」いや「イアン・アンダーソンの青春時代を描写したアンダーソン版『若き芸術家の肖像』だよ」という意見もあり。
テーマが両方にまたがっているとしても、おそらく後者が主軸になっているのではないでしょうか。将来は天井桟敷の吟遊詩人になって、もしシニカルな歌を歌ったら、と言っている少年が登場するところからも。
この曲の楽器も素晴らしく、重厚なのに切れのいいリズム・セクション特にドラミング、フルート、ピアノ、ストリングス、ギター、どれを取ってもいいもの聞かせてもらったという感があります。サビの美しさは絶品です。
ちなみにこの曲の終りにイアン・アンダーソンがこの曲を口ずさみながらスタジオを出て行こうとして「I can’t get out!」と叫んでいるのが録音に入っているのはどういう趣向なのでしょうか。
そのあと僅か37秒の小曲「Grace」を経て、リマスター版でないきつね亭のアルバムは終了します。
まとめ
伝統的な英国のフォークとハードロックの融合、確かな演奏技術と全体的を彩るフルートの音色の美しさ。イアン・アンダーソンの歌手としての魅力。
にもかかわらず何故かジェスロ・タルは過小評価されているような気がします。周囲のロック好きからもタルが好きだ、という話が出たことがありません。
70年代初頭の「アクアラング」、「ジェラルドの汚れなき世界(Thick as a Brick)」と並んでこの「Minstrel」も」ぜひ聴いていただきたい秀作です。
音楽ブログ近日に再開します!
我が家はアパートの最上階で山や木々の眺めがよく気に入っているのですが、先日大雨の日にまさかの雨漏りに見舞われました。5−6ヶ所から同時に雨水が吹き出し、あわや天井が崩壊・落下するのではと一時は本気で心配になりました。
管理会社が隣の空き部屋を仮住居として提供してくれましたので、なんとか生活できたものの‥。運悪く床に置いてあったラップトップを開けて見たら雨水を存分に吸ってしまっていてビクとも動きません。
何とかパワーボタンを押し続けてやれやれ立ち上がったと思ったら、凄まじいビービー音とカラフルな横縞の画面。今度はシャットダウンできないし。
仕方なくアップルのジニアス・バーに持って行ったら、「このコンピュータはビンテージですね、修理は外注に出しますのでざっと1500ドル(16万円ぐらい)かかります。いっそ新しいラップトップお買いになったら」って、ビンテージとか稀少価値がありそうなカッコいいボキャブラリーですが、要は「古い機械なのでいい加減諦めましょうよ」という話。
ちょっと!簡単に言うけど立派に使えてたんですけど(怒!)
確かに7年前のライオンというOSです。さすがに今だにネコ科動物シリーズのOSを使っている方は多くはないでしょう。
慣れ親しんだマシンを泣く泣く諦め、新しいMACBOOK PRO購入。
幸いにも賃貸保険会社が新しいマックプロの金額の殆どをカバーしてくれたうえアパートの管理会社が仮住まいの間の家賃をチャラにしてくれると約束してくれたので、実質的な出費はないと(多分)思うものの、長年愛用のマックがおシャカになるのが悲しすぎます。過去データもブログ記事のドラフト(少いのが幸い)も写真もGone Forever。
週一の音楽ブログを大分ご無沙汰してしまいました(スマホで記事に慣ればよかった)が、今後ともよろしくおねがい致します!
アイルランドが生んだ伝説のギタリスト、ロリー・ギャラガーの『Calling Card』

今晩は、ヴァーチャル・パブのロンドンきつね亭です。
今日のミュージシャンはアイルランド出身のロリー・ギャラガー。
よく聞く逸話によれば、ある人がジミー・ヘンドリックスに「世界一偉大なギタリストと言われるのはどんな気分ですか?」と尋ねたところ、「それならロリー・ギャラガーに訊いてみろ」という返事が返って来たとか。
間違いなく世界のトップクラスの実力をもつブルース・ギタリストでありながら知名度では今ひとつの感があります。
『コーリング・カード』(1976)は8枚目のアルバム。
ディープ・パープルにいたロジャー・グローヴァーがギャラガーと共同でプロデュースに参加しています。
今日はやはりアイリッシュ・ウィスキーですね。ブッシュミルズのオンザロックでまったりとおくつろぎください。
ドゥー・ユー・リード・ミー(Do You Read Me)
ドラムのビートの間にギターが特徴的な入り方をしてくる一曲目は「Do you read me」。
心地よくて好きな曲です。ところによってイーグルスの「Life in the Fast Lane」に似ていたり、サビがバドカンの「Rock Steady」に似ていたりとブルースというよりもロックの曲調ですが、ギターと歌はブルースです。
途中のギターのソロがすごくいい。ギターがのびのびと歌っている感じです。
キーボードとの掛け合い、最後のユニゾンも楽しい。
ロリー・ギャラガーの声は、優男風のルックスに似合わずブルース・スプリングティーンに近いしゃがれ声で、この曲には合っています。
アルバムを通してみるとそれほど歌が巧いとは思えないのですが、この曲のボーカルには不思議と引き込まれます。
ライブではすさまじい神業を見せています。
Rory Gallagher - Do You Read Me (Rock Goes To College, 1979)
2曲目の「カントリー・マイル(Country Mile)」はロカビリーというのでしょうか。
エルヴィスがやりそうな、当時の表現で言えばイカした曲ですね。
これも声質に合った曲です。
短いピアノ・ソロがいい。後半のギターのフレーズはジェフ・ベックを思わせるものがあります。
ドラムの音が何となくバタバタしていますがそういうものなのでしょうか。
「コーリング・カード (Calling Card)」
表題作の「コーリング・カード」。私的にはこのアルバム中最も好きな曲です。
スタジオ録音のはずなのに、どこかのジャズクラブで演奏しているような雰囲気を醸し出しています。
ジャズの要素のあるブルースで、ギターもピアノもアドリブで掛け合いをやっています。
この曲のピアノ・ソロもギター・ソロ秀逸です。ベースの動きも好きです。
「シークレット・エージェント」。シャッフルのノリのいい曲です。
自分の彼女がシークレット・エージェントを使って自分を見張っている。家の前で待っていて、どこに行っても付いてくる。
うまくいかない恋だとか失恋の歌が多いブルースの中にあって異色の歌詞です。
右のスピーカーからくる低音のギターが左のスピーカーの高音のギターと絡んでツイン・リードのような効果を出しています。
そういえば曲調もツイン・リードで有名なウィッシュボーン・アッシュの「ジェイル・ベイト」に似てる気が。
次の「ジャック・ナイフ・ビート」はファンキーな曲。
独特のカッカッというギターとドラムのシンコペーションを効かせたイントロ、その後のギターソロがカッコいい。
スタジオでジャム・セッションをやっている感じで、アドリブでやっていると思われるギターとピアノの絡みが絶妙です。
このアルバムのあと、全5作のアルバムで一緒にやってきたキーボードのルー・マーティンとドラマーののRod de'Ath と袂も分っていますが、ここで聴く限り息はぴったり合っていると思うのですが。ロリー・ギャラガーはこういうアドリブがかなり好きで得意としていますね。
「エッジ・イン・ブルー(Edge in Blue)」。この曲、イントロのギター・ソロの美しさ、ロック史に残るレベルではないでしょうか。
むしろギター・ソロの延長でインストゥルメンタルの曲として入れてほしかった。
バーレイ・アンド・グレープ・ラグ(Barley and Grape Rag)
最後の「Barley and Grape Rag」はアメリカ南部のカントリ―・ブルースの原点を思わせる曲です。
マディ—・ウォーターズ辺りのブルース・ミュージシャンに影響を受けてきたロリー・ギャラガーらしい。
Barleyはウィスキーの原料の大麦、Grapeはワインの原料のブドウ。彼女に冷たくされた、つまんねえ、今夜は街に出かけてとことん酔いつぶれてやるぞという歌です。
1930年代のビンテージのリゾネーター・ギター、縦乗りベースとシンコペ満載ドラム、ハーモニカ、ピアノで昔の酒場の様子が目に浮かびます。
ステージではギター一本でやっている画像が残っていますが、そちらもなかなか味があります。
barley and grape rag " rory gallagher live at rockpalast 1977
最後に
ロリー・ギャラガーのギターの音は一度聞いたら忘れられません。
洗練されてないのにカッコいい、まさにブルース・ギターの王道を受け継ぎ、次世代につないだ人という印象です。
演奏を生で見たかったと思います。
残念ながら彼は1995年に47歳の若さで肝臓障害で命を落としています。飲酒が主な原因だったというのもアイルランド人らしいとも言えるでしょう。
ジェネシス『フォックス・トロット』が今年のトリです

今晩は。ヴァーチャル・パブのロンドンきつね亭です。
ジェネシスはずっと食わず嫌いできたバンドでした。
曲の構成も詞も面倒そうだったのに加え、70年代のピーター・ガブリエルの可愛くなくなったエリマキトカゲみたいなステージ・メイクと衣装がグロテスクで好きになれなかったのですね。
ですが、きつね亭の表看板をに図柄を無断借用させていただいている以上、無視も出来ません。というわけで今回は『Foxtrot (フォックス・トロット)』でいってみます。
内容に入る前にこのジャケットの図柄ですが、表紙はマダム然としたキツネが流氷だか岩だかの上で余裕のポーズを取っていますが、裏面では岸辺にキツネを追いつめた狐狩りの貴族らしき数人が猟犬とともに描かれています。

一人はなぜか白いハンカチで涙をぬぐっています。その隣の騎乗の二人はどうみても人間ではない。一人はサルのような耳の異形で、もう一人は緑色の顔をした宇宙人らしき面相です。
奇妙な面白いイラストですが、ジェネシスのメンバーからは自分たちの音楽に合わない、絵にプロの技巧を感じないなどと至極評判が悪かったようです。
今日はフォックス・トロットという名のカクテルで、弊店のはレモン・ジュースとオレンジ・リキュールが入ります。
「Watcher of the Skies (ワッチャー・オブ・ザ・スカイズ)」
パイプ・オルガンにも似たメロトロンの荘厳で一種悲壮感のある音のイントロがしばし続いた後に、オルガン、ベース、さらにドラムがタカタ、タッタッタ、タカタ。タッタとスタッカートのリズムを刻み始める。モールス信号だと言う人もいます。
最初からえらい密度の高い曲です。やがてベースとリズムギターにモールス信号をまかせてドラムが違うリズムを叩き始めている。ポリリズムというのですか、なるほど。
めちゃめちゃ威圧感のある曲なのだけどそれぞれの楽器の音がとても美しい。フィル・コリンズのドラム、難易度の高いことしてると思うけど音が軽妙洒脱で綺麗です。ギターの入り方もネックをグワーと擦り上げるところもカッコいい。
歌詞は人類が滅亡したあとの地球を訪れる宇宙人の視点で描いています。「おそらくトカゲは尻尾を切ったのだ」という歌詞は「地球が存続のために人類を切り捨てた」という意味でしょう。
「空を見つめる者」は人ではなく地球外生命。
とするとあのモールス信号の拍子は人間が最後に放ったSOSを暗示していたとか。
YouTubeで当時のコンサートを見ると、宇宙人を演じるピーター・ガブリエルが頭の横にコウモリの羽根(これじゃ宇宙人じゃなくて悪魔だ)をつけています。途中でタンバリンをお面の代わりに顔に当てて妙なパントマイム。
意外に愛嬌があります。強烈なインパクトのある曲なので多くのコンサートの第1曲目として演じられたというのも納得できます。
「Time Table (タイム・テーブル)」
地球外生命の視点だった前曲に続き、この曲の主役は長い年月を経て歴史を見てきたオーク材のテーブル。
昔々、王と王妃が黄金のゴブレットで葡萄酒を飲み、勇者は貴婦人を涼しげな木陰に誘い‥武勇が尊ばれ伝説が生まれ、栄誉が命よりも重んじられていた頃、とキャメロット的な世界が語られる一方、サビの部分では何故我々人間っていうのは死ぬまで分らないんだろうね、時代は移ってもやっていることは同じ、自分たちの戦いがいつも崇高だと信じているなんて、と人間の愚かさを自嘲的に歌っています。
トニー・バンクスのピアノを中心に展開する心地いいメロディ。途中ベースの高音がキーボードと美しく絡んでいる箇所があるんですが、このチリチリというキーボードが何なのか分らない。
ネットで調べてみたらやはり「分らない」という投稿がいくつかあって、中には「トイ・ピアノ」を使っているんじゃないかなどという意見も。
多くの人が「これはピアノの中の弦をギターのピックで弾いている音だよ」と回答していて、おそらくその辺りかもしれません。演奏者による真相解明はなされていないらしいです。
続く3曲目の「Get'em out by Friday(ゲッテム・アウト・バイ・フライデイ)」はピーター・ガブリエルが1人3役の声色を使い分けて、賃貸集合住宅を買収して店子を追い出したい企業家、追い出しを請け負っている業者(Winkler)、当惑している借家人の夫人を演じています。巻き舌で借家人に迫っているウィンクラーのアクの強さに笑える。ステージで見たらガブリエルの表情の七変化もみられてさぞ面白いでしょう。この曲はオルガンも秀逸、ドラムのリズムも凄い。
「Can-Utility and the Coastliners (キャン・ユーティリティ・アンド・ザ・コーストライナーズ)」
12弦ギターのアルペジオで始まる美しい曲。
メロトロンが奏でる弦と笛の透明感、中盤以降のオルガン・ソロが何ともいいです。
途中でフィンガー・シンバルの可愛らしい音が入っています。
11世紀初めにデンマーク、イングランド、ノルウェーを束ねた北海帝国の王、デーン人のクヌート大王の故事がテーマになっています。
クヌート王はある時玉座を海辺に置いて、打ち寄せる波に向かって「退け。我の足も衣も濡らすな」と命じました。もちろん波は王様の命令など知ったことじゃありませんからどんどん打ち寄せて来ます。
王様は波から飛び退いて、臣下に向かって「見ただろう、王の権力なんてどれほどの物でもない。天、地、海を従わせる神だけが永遠の権威なのだ」と言ったそうです(参照Wikipedia)。配下の国々にただ追従する愚かさを教えようとしたエピソードとして知られます。
表題のCAN-UTILITYはCANUTE大王の名前の綴りと現代のユティリティ(公共事業)をもじっていますが、現代のビジネスとの関連性は不明です。
ピーター・ガブリエルのアクの強いヴォーカルに少々お腹いっぱい、というタイミングでスティーブ・ハケットのアコギ曲「Horizons(ホライゾンズ)」が入ります。
イエスの「ムード・フォー・ザ・デイ」のようなスパニッシュ・ギターのテク見せまっせ、の曲ではなく、懐かしく緩やかで、次に控える大作「サパーズ・レディ」を前にした箸休めのような曲ですね。
「Supper's Ready (サパーズ・レディ)」
一言で感想を言うと、これは圧巻です。
7つのパートに分かれた23分の組曲ですが、何度聴いてもよいというか、聴けば聴くほど味わい深い。
最初は久しぶりに会ったカップルの奇妙な違和感から、農民とエセ科学宗教家との小競り合い、ヨハネの黙示録、ウィリアム・ブレークのニュー・エルサレムのような世界と曲のテーマが途方もなく広がる一方で、第1章と最終章に繰り返されるメロディは耳になじみやすく全体を綺麗にまとめるのに成功しています。
印象に残るのは、まず第1章目「ラバーズ・リープ」の終盤です。ガブリエルのボーカルが終った後、ハケット、バンクス、ラザフォードの12弦ギターのアルペジオが続く中、エレクトリック・ピアノとコーラスが入ってくる。
どこか中世の村をイメージするようなフォークの調べが、川のせせらぎのようでもあり、精巧な細工のようでもあり、何とも繊細な美しさです。
第4章の終盤でナルキッソスが花(水仙)に変えられてしまった、というギリシャ神話の一説が歌われ、ガブリエルが「花(Flower)?!」とう台詞とともに花の被りものを付けて出てくる。
そこから始まる舞台喜劇のような章「ウィロー・ファーム」のヴォーカルは達者につきます。「チャーチルがドラッグの格好をして」という部分には苦笑ですが、次から次へと繰り広げられる連想ゲームのような言葉遊びの文学性、表情豊かな歌唱は舞台芸術としても第一級といえるのではないでしょうか。ガブリエルは当初苦手意識があったのに、いつのまにか憎めない印象になってきて度々笑わせられたり。
しかし何と言ってもインパクトがあるのはそれに続く「アポカリプス9/8」という章。タイトル通り8分の9拍子でリズム・セクションが入っていますが、ここのフィル・コリンズのドラミングとバスドラの音がすさまじい。
そこに入るオルガンソロ。トニー・バンクスはこの部分はキース・エマーソンのパロディで作った、と言っていますが、そこは今ひとつぴんときません。
リズム・セクションの力強さとオルガンのコンビネーション、はじめ4分の4拍子で繰り返すキーボードのフレーズは東洋風の響きもあり、石棺から兵馬俑が出て来て行進を始めそうな、そんな迫力です。
Genesis - Melody '74 Live - Supper's Ready (1st Gen. Copy) Remastered
まとめ
ピーター・ガブリエル時代のジェネシス、面白い。面白すぎる。
人類滅亡後の地球から、王侯貴族の集う大広間、北海帝国の海辺、農民とエセ科学宗教家との争いへと視聴者を誘うイマジネーションの幅にも、それを支える演奏技術の確かさにも感服。
とくにバンクスのキーボードとコリンズのドラムが。そしてガブリエルのドタバタと被り物をかぶりながら演じている芸人のような茶目っ気と曲にぴったりあったヴォーカルにも。
繰り返し聴きたい密度の濃いアルバムでした。
さて暮れも押し迫りました。
皆様どうぞよいお年をお迎えください。
2018年もロンドンきつね亭にご来店をお待ち申し上げております。
ムーディー・ブルースの「セブンス・ソジャーン」は不朽の名盤

今晩は。倫敦ヴァーチャル・パブのきつね亭です。
今晩の名盤は、ムーディー・ブルースの『Seventh Sojoun(セブンス・ソジャーン)』です。
この記事をヒットしてくださった方はご存知かと思いますが、ムーディー・ブルースはイギリスのバンドで一般的にプログレの草分けのような扱いになっています。
70年代の最盛期のメンバーはジャスティン・ヘイワード、ジョン・ロッジ、マイク・ピンダー、グレアム・エッジ、レイ・トーマスの5人。
しばしのソロ・休眠期を経て80年代にも数枚の佳作アルバムを出しています。
ムーディーズのベスト・アルバムはこの8枚目『セブンス・ソジャーン』か7枚目の『童夢』(当ブログのタイトルのバックにある子供のイラストのジャケね)かと悩ましいところですが、「Isn't Life Strange(神秘な世界へ)」「ユー・アンド・ミー」「ロックンロール・シンガー」が入っているという点でこのアルバム一押しです。
では聴いてみましょう。
今夜のカクテルはその名もムーディー・ブルー。
ウォッカ、ピーチ・シュナップス、ブルー・キュラソーとアップル・ジュースでお作りします。
まず独断ながら第1曲目の「失われた世界(Lost in a Lost World)」と2曲目「新しい地平線」は軽く聞き流しても構いません。
マイク・ピンダー作の一曲目は反ヘイトのメッセージ・ソングですが、曲調がやや時代を感じさせます。はっきりいうと、サビの部分は昭和の歌謡曲を彷彿とさせます。
2曲目はジャスティン・ヘイワード作のきれいな曲ですが、やや冗長な印象を免れません。
「For My Lady(フォー・マイ・レディー)」
さて、この辺りからムーディー・ブルースの本領発揮の感があります。
作詞作曲を手がけたレイ・トーマスがフルートとヴォーカルを担当していますが、なんという美しい旋律。
ムーディーズというとどうしてもジャスティン・ヘイワードとジョン・ロッジのイメージが前面に出ていて、他3名の存在は悲しいかな地味なのです。 が、地味方のレイ・トーマスがこんなに甘く心地よい声をしているとは。
フルートとアコギ、そしてメロトロンに代わるチェンバリンによるオーケストラ。バックのコーラスの美しさ。
愛する女性への想いを航海に例えているあたりも旋律もいかにも英国フォークの伝統を踏襲した曲作りで、時代を感じさせないラブ・ソングといえるでしょう。
「Isn't Life Strange?(神秘な世界へ)」
私的にロック史上全カテゴリーの曲で好きな曲の5番以内には必ずランクインするのがこの曲です。
神秘な世界へ、という陳腐な邦題はこの際どうでもいい。
「人生って不思議だよね」なんです。
苦しみ、悩んで悪戦苦闘して、でもその日があったから今ここにこうしている。
貴女の瞳にうつる存在でありたかった。思いかえすと貴女はそこにいた。でも今僕らはここにいる。(自分ながら陳腐な訳ですが)
サビの部分、It makes me cry, cry ,cryから、Wish I could be in your eyes/Looking back there you were, and here we areに胸をつかれます。泣きたくなります。
切ないけど哀しくはない。男女の再会の歌であると同時に愛と再生の歌なんですね。
チェンバリンによるバックグラウンド・オーケストラの美しさ、力強い男声コーラスにかぶさるメローなギター・ソロの妙。
ああ生きていてよかった、この曲がまた聴けた‥というと大げさですが。
作詞作曲のジョン・ロッジさんにありがとうと言いたくなります。

「You and Me (ユー・アンド・ミー)」
エレキ・ギターのソロとチェンバリンの印象的なイントロではじまるヘイワードとエッジの共作によるアップテンポの曲。
「東洋に葉のない木があり、陽光の下に家のない人がいる。谷は山火事で燃え、そこから物語は始まる」
と、何だか神秘的な歌詞です。ウィキペディアによると枯葉剤を使ったベトナム戦争の暗示とのことですが、ピンと来ません。
大いなる父により創造され、その子の愛によって祝福されたこの世界を畏怖をもって眺めようというキリスト教的な世界観も出てくる。
失敗はゆるされない、決して決して止まってはいけない、と言っているのでやはりメッセージソングなのでしょう。
ジャスティン・ヘイワードを中心としたコーラス、ギター・ソロ、チェンバリンとともにリズム・セクション、とくにリズム・ギターとパーカッションが効果的に入っています。
続く「Land of Make Believe(虚飾の世界)」でもコーラスが活きていて、ヘイワードの美声が発揮されています。
アコギ、フルート(合成?)に加え、チェンバリンによるオーケストラ・サウンドの広がり。ここでもヴォーカルと重なって入ってくるギター・ソロが魅力的です。
「I am just a singer in a rock'n roll band (ロックン・ロール・シンガー)」
ジョン・ロッジによるこの曲を最後にもってきたのはグッジョブです。
このアルバムのいくつかのメッセージソングに、ムーディーズはこの曲で「私はロック・バンドのシンガーに過ぎないよ」と答えています。
政治家でもなく有力者でも軍人でもない。でも音楽というメディアを通じて異なる言語・文化の間に橋を築いているよという彼らの矜持が歌詞から伝わってくるのです。
前の曲の遠くかすかな笛の音の名残にパタパタとドラムがかぶさっていくイントロが面白い。
曲全体を流れるギターとオーケストラ・サウンド、中間に入るギター・ソロも耳に心地よく、ノリのいい曲です。
終わりに
日本語のウィキペディアを見たら「本当にプログレッシブなバンドはピンク・フロイドとムーディ・ブルースだけだ」というジミー・ページの台詞が載っていて意外な気がしました。
ピンク・フロイドは分かるとして、自分の中ではクリムゾンとフロイドあるいはクリムゾンとイエスの組み合わせが挙るような気がしていたので。
確かに他に先駆けてメロトロンを駆使した音作りをしていたのでプログレというジャンルに属するのでしょうけれど、それはたまたまマイク・ピンダーというキーボード奏者がいたからで、ほかのメンバー達もはたして意識してプログレの方向を目指していたんだろうか?と。どちらかというとソフト・ロックの要素もあって、ソフトよりのプログレというか。まあジャンルは関係なく、ムーディ―・ブルースは本当にいいです。
おまけのクリスマス・プレゼントです。
この時期にちなんでムーディー・ブルースの『December』というアルバムからクリスマスの曲を2曲。
「In the Quiet of Christmas Morning」はバッハの「主よ人の望みの喜びよ」のアレンジです。
The Moody Blues - In the Quiet of Christmas Morning (Bach 147)
そしてもう一曲は「スピリット・オブ・クリスマス(Spirit of Christmas)」。ジョン・ロッジの美しい曲です。少々むごい画像が入っているので閲覧は注意して下さいね。クリスマスの本当の意味を伝えている曲だと思います。
The Moody Blues - The Spirit of Christmas
このアルバムにはホワイト・クリスマスはじめクリスマスの曲が11トラック入っています。
リック・ウェイクマン『ヘンリー八世の六人の妻』―ドロドロ修羅場のお妃たち

今晩は。ヴァーチャル・パブの倫敦きつね亭です。
いきなり本題と全然関係ない話で申し訳ないのですが、昨日家にハミングバードがやって来ました。
ベランダに面した網戸の辺りに仕切りにぶつかっている飛来物体があって、「やだなー、こんな大きなスズメバチ?」とよく見たらハチではなくハチドリ(ハミングバード)。
生まれて初めて実物を見ました。すごく小さくて一生懸命羽ばたいている様子がすごく可憐。南かリフォルニアや中南米にはいると聞いていたけど、北カリフォルニアの我が家にも来るとは。
写真を撮ろうと思った途端にスイーッと飛んで遠くの木立に消えてしまいましたが、なんだか楽しい気分。
さて今晩の名盤は、リック・ウェイクマンの『ヘンリー八世の六人の妻』(1973)です。
リックがイエスのメンバーとして『こわれもの』『危機』を出したあとにリリースされたソロ・アルバムです。
アメリカ・ツアーの際に移動の飛行機で読んだヘンリー八世の本に出てきた妻の一人アン・ブーリンの章を読んだときにかねてから構想していた音楽が脳内でバックに流れ始めてたのがアルバム・テーマ選択のきっかけとなった、とCDジャケにある。
ヘンリー八世は16世紀のイギリスの国王で、エリザベス一世の父にあたる人です。

私がヘンリー八世です。
カリスマ性のあるな国王ではあったが、夫としては最悪の部類で、浮気はやりたい放題、妻の侍女達に片っ端から手をつけるわ。六人の妻のうち2名は追い出され、2名は不義のかどで処刑されています。
リック・ウェイクマン本人の談では、当時ヘンリー八世関連の本を読みあさり六人の妻の一人一人にイメージを膨らませて曲を作ったとのこと。
アルバムにはイエスのクリス・スクワイア、スティーブ・ハウ、アラン・ホワイト、ビル・ブルーフォードを含め、ベーシスト4名、ドラマー3名、ギタリスト3名、パーカッション2名が参加しています。
多くのミュージシャンを起用したのは、「ソロ・アルバムを作る時、同じメンバーで全曲やるっていうのは好きじゃない。同じパターンの曲になっちゃうからね。だから自分が今まで一緒にやってきた優れたミュージシャンにはできるだけ大勢に入ってもらうことにした」のだそうです。
各お妃の紹介も含め長くなりそうですが、全曲聴いてみたいと思います。
今日はヘンリー八世の娘で「血なまぐさいメアリー」の異名をとったメアリー一世(エリザベスの異母姉)にちなんでブラディ・メアリーのカクテルで参りましょう。
I. アラゴンのキャサリン(Catherine of Aragon)
キャサリンはアラゴン(現在のスペインの一部)国王のお姫様。もともとヘンリー八世の兄のアーサーに嫁いできました。 運悪く兄は15歳でインフルエンザをこじらせて夭折、政治的な理由でヘンリーが兄嫁キャサリンを貰い受ける形になりました。
ところが世継ぎの男子を渇望した王の意思に反して何回かの流産の末に生まれたのは女児ひとり(のちのブラディ・メアリーことメアリー一世)。
国王の関心は徐々にキャサリンから離れ、その侍女だったアン・ブーリンに移ります。キャサリンは追い出され、侍女が王妃の部屋に居座ります。
キャサリンは神への信仰を胸に一人寂しい余生を送ることになりましたが、50年の生涯はヘンリー八世のお妃のなかでは異例の長さと言えます。
のっけから、これはイエスのスピンオフかと思わせるクリス・スクワイアのリッケンバッカーの固いベース音とビル・ブルーフォードのドラムのイントロ、リックのオルガン。
それに続いて華麗で優美はピアノのソロが奏でられます。いかにもクラシック音楽の教育を受けてきた人という印象。ピアノ・ソロの後ろにズン、ズンと入っているクリスのベースも渋くていい。
やがてムーグのグワーグワー音による主旋律。このバックに流れるこれも多分シンセサイザーの薄いベールのような音、時折入るビブラフォンのような合成音が何ともいえない美しさです。
ふたたびピアノ、ベース、バックに女性のコーラス。女性ヴォーカルもこのアルバムにクレジットされていますが、これはメロトロンではないでしょうか?
最後は再びピアノで美しく終っています。寂しい余生だったとはいえ、アラゴンのお姫様の人生らしい優美な曲です。
ちなみにこの第1曲目に、スティーブ・ハウのギターも入っているはずのなのですが、何度か聞き直してもピンと来ませんでした。
II. クレーヴスのアン(Anne of Cleves)
キャサリンの後釜に座ったのはアン・ブーリンですが、このアルバムは年代順になっていません。
第2曲のクレーヴスのアンは第4番目の妻です。デュッセルドルフから嫁いだこの女性は、結婚前に受け取っていた美しい肖像画とあまりに違っていたため、ヘンリー王は「嘘だ!」と叫んで不機嫌になったとか。
ホルバイン作の肖像画を見る限りさして不細工ではありませんが、いまひとつ華がないかも、です。
結婚後すぐに王の関心はクレーヴスのアンの侍女キャサリン・ハワード(八世の妻にはアンが2名、キャサリンが3名。ややこしいですね)に移ったため、結婚後半年で離婚するはめに。その間床入りもなかったらしい。クレーヴスのアンはすんなり離婚を受け入れ、「王の妹」という称号と相当の慰謝料を受け取ってその後17年の余生を経済的に不自由することもなく暮らしました。
ジャズタッチの曲で、リックのオルガンが中心になっています。ベースはデイヴ・ウィンターというセッション・ミュージシャンですが、この人のベース・ラインがすごく面白く、リックのオルガン・ソロとうまく絡んでいます。パーカッションもアラン・ホワイトのドラムものっています。面白い曲なのですが、地味なドイツ人花嫁のイメージとどう結びつくのかは分りません。
III. キャサリン・ハワード(Catherine Howard)
わずか19歳で明るく開放的な性格のキャサリン・ハワードにヘンリー王は夢中になりおびただしい数の宝石や土地を与えます。
ところがキャサリン、以前の恋人を秘書がわりに雇い関係を続けていた上に、遠縁にあたる別の男性とも浮き名を流していることが王の耳に入ります。可愛さあまって憎さ百倍、と王様は思ったのでしょう。
キャサリンは最後まで姦通を否定したものの、ウィキペディアによると斬首刑になる直前に「どうせならカルペパー(遠縁の愛人)の妻として死にたかった」と王の前でスピーチをしたといいますから、大したものです。
それにしても数年前に同じく王の寵愛を受けていたアン・ブーリンが姦通罪で死刑になっているのに何で同じことをしますかね。恋は盲目なのか、自分だけはバレないと思ったのか。ちなみに相手の男は記事に書くのをはばかられるような凄まじくグロな方法で処刑される筈のところを、王の慈悲とやらで減刑されて普通の斬首に処せられたとか。
この曲は牧歌的で優しいピアノとギターのメロディから始まり、何度か転調しながらピアノ、シンセサイザー、ピアノ、シンセサイザー、と目まぐるしく入れ替わりながらも徹頭徹尾、明るい曲です。
ストローブスの元同僚からデイヴ・カズンズが電子バンジョーで、チャス・クロンクがベースで参加しています。途中のブギウギのパートなど、リック自身かなり楽しみながらピアノを弾いている印象。
凄惨な最期を迎えた女性というよりも、王に寵愛されて愛人も二人いて、人生が楽しくてしかたないという若くて無防備な女の子だった時期の曲に聞こえます。実際、案外あっけらかんとした女性だったのかもしれません。不倫が露見してからも「なんでー?」とか言っているような。
後半に入る鐘の音も葬礼というよりも婚礼の鐘のように明るい将来を示唆しているかのよう。最後に主旋律をメロトロンによるホルンが静かにゆっくりと奏でて曲が終わります。

リック・ウェイクマンのトレードマークは金髪ロン毛とぐるり周囲のキーボード
IV. ジェーン・シーモア (Jane Seymour)
ジェーンはクレーヴスのアンやキャサリン・ハワードより前に妃となった女性です。穏やかで柔和、気の弱い女性であったらしい。
ヘンリ―八世待望の世継ぎである男児を出産したことで王太子の母として大事にされましたが、産褥から回復することなくこの世を去ります。ヘンリー八世と同じ墓に入った唯一の妻です。
これはバロックの曲。セント・ジャイルズ・ウィズアウト・クリップルゲート教会のパイプオルガンでJ. S. バッハを思わせる荘厳な曲が奏でられ、チェンバロが入り、オルガンとチェンバロが絡みながら曲が展開していきます。
オルガン、チェンバロにドラムが入っていくのが面白い。後半怒濤のようにシンセサイザーが入るもののバロック音楽から離れず、パイプオルガンとチェンバロの美しい旋律のまま曲が終ります。
ジャンルとしてはロックに部類されるリック・ウェイクマンですが、チェンバロとパイプオルガンのこういう曲、きっとやってみたかったんだろうなと思わせます。
V. アン・ブーリン(Anne Boleyn)
アン・ブーリンはヘンリー八世の最初の妻であるアラゴンのキャサリンの侍女として宮廷に入り国王の寵愛を受けます。王妃になりたいという彼女の要求を王が受け入れたためキャサリンは追い出されます。
そもそも兄アーサーの未亡人だったキャサリンを嫁にしたことをローマ教皇庁は特例として認めていたのですが、この妻を離婚することを教皇庁は認めなかったんですね。
怒ったヘンリー八世はカトリック教会と決別し、これが英国国教会の発祥です。王様のワガママで誕生した教会、何だか有り難みに欠けるといったらイギリス人に怒られるかもしれませんが。
さてアンは同じ年に女児を授かり、男児を切望していた国王を大いに失望させます。この女児こそがのちに英国の黄金時代の君主となるエリザベス一世なのですから皮肉なものです。
さらに彼女自身の短気な性格ときついもの言いも災いして、ヘンリーは今度はアンの侍女だったジェーン・シーモアに心を移します。歴史は繰り返す。王様も懲りない。
結婚から4年目、アンはロンドン塔で処刑されます。罪状は姦通のほかに反逆罪、黒魔術まで入っています。アンはその激しい気性から敵も多かったらしく、本当なのか嵌められたのかは知る由もありません。
6人の中でもとりわけドラマチックな人生じゃないでしょうか。王妃でいたのが約1000日で、『1000日のアン』という映画にもなっています。
寂しげなピアノ・ソロのイントロからシンセサイザー、ドラム、ベースがフォルテシモで入り、アンの穏やかならぬ人生の先行き表しているようです。
やがてメロトロンとベースをバックに美しいピアノソロ。女性コーラスから数小節は彼女の人生の絶頂期、シンセサイザーの長いソロが波瀾万丈の人生を思わせます。やがてシンセサイザー、ドラム、鐘の音で死が訪れます。
そのあとにピアノの心安らぐメロディにのせて女性ヴォーカルの賛美歌。リック・ウェイクマンはアン・ブーリンの葬式に参列している場面を夢に見て、その時聞こえた賛美歌を曲に落とし込んだとか。ただし16世紀当時の英国には賛美歌のようなものは存在しなかったと後で調べて分った、と語っています。
VI. キャサリン・パー(Catherine Parr)
ヘンリー八世が52歳のときに娶った最後のお妃です。
馬上試合の傷の後遺症に苦しむ王を看護し、安らぎを与えたり時には笑わせたりする一方、これまで宮廷になかった調和のために尽力したと書かれています。
最後はこの后に看取られてこの世を去りますが、王様は最後にいい奥様を娶りましたね。継子メアリー、エリザベス達にも優しく、慕われていたといいます。
王の死後、昔の恋人だったトーマス・シーモア(ジェーンの兄)と結婚しますが、女児出産後に産褥熱で死去しています。

顔も6人中一番可愛らしいような気がします
これもドラマに富んだ曲。IIと同じデイヴ・ウィンターの特徴のあるベース、いかにもアラン・ホワイトらしいドラム、オルガンのイントロからオルガンのソロ、叩き付けるようなピアノと混成合唱と目まぐるしく変化します。
そのあとにどこかで聞いたようなメロディがシンセサイザーで繰り返される。どこかで聞いた旋律なのにどこで聞いたか思い出せない、と焦っているうちにドラム、ベース、ピアノ、メロトロンによる鐘をフィーチャーした数小節。
シンセサイザーによる木枯らしのよう切り裂く音のあとに、小川の水を思わせるピアノ美しい音色。またまたどこかで聞いメロディが出て来て何だったっけと思っているうちに曲はクライマックスを迎えます。
******************
長い記事になりましたが、もしここまで読んで下さった方がおられたら深謝いたします。
ギター、ベース、ドラムといった楽器のプレーヤーがジャズ、ロック、ブルースといった軽音楽からスタートしているのに対し、キーボード・プレイヤーには子供のころからピアノを習っていた、とか音楽学校で教育を受けたなどクラシック音楽を基礎からやっている人が多いですね。リック・ウェイクマンもその一人。ロイヤル・カレッジ・オブ・ミュージックに在籍しピアノとクラリネットを学んでいます。
このようなロックの世界に入ったピアニスト、キーボードプレイヤーってクラシックの分野の人からはどのように見えるのか、ちょっと興味があります。邪道なのか、テクニック的には劣るのか、あるいは面白いものなのでしょうか。
バッド・カンパニーの1枚目はフリー+モット・ザ・フープルの勝利
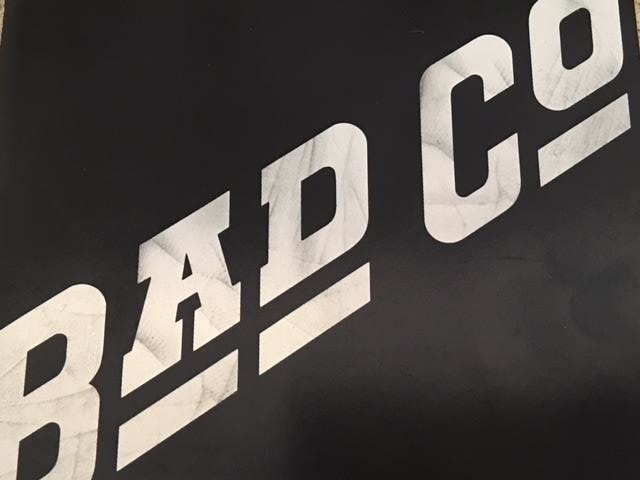
1 キャント・ゲット・イナフ(Can't Get Enough)
2 ロック・ステディ (Rock Steady)
3 レディ・フォー・ラブ (Ready for Love)
4 ドント・レット・ミー・ダウン (Don't Let Me Down)
5 バッド・カンパニー (Bad Company)
6 ザ・ウェイ・アイ・チューズ (The Way I Choose)
7 ムーヴィン・オン (Movin' On)
8 シーガル (Seagull)
今晩は、ヴァーチャル・パブ倫敦きつね亭です。
今夜のアルバムはバッド・カンパニーの1枚目『バッド・カンパニー(Bad Company)』です。
バッド・カンパニーは元フリーのポール・ロジャース(v、piano、g)とサイモン・カーク(d)、元モット・ザ・フープルのミック・ラルフス(g)、元キング・クリムゾンのボズ・バレル(b)による4人編成で、結成当時はスーパーグループと呼ばれていました。
きつね亭はバッド・カンパニーには少し思い入れがあります(ここからちょこっと個人的な自慢です)。
昔々のことですが、ミュージック・ライフというどちらかといえばミーハー系の音楽雑誌で懸賞論文を公募してまして、私はバドカンに関する論評を書いて応募しました。
フリーとバッド・カンパニーの魅力を比較したような、今から考えれば顔から火が出るような拙い内容だったと思いますが、選考委員の音楽評論家の方々の目にとまって何故か入選。
当時フリーに傾倒しているような若い女の子は多くなく、珍しかったのかもしれません。
雑誌に文章が掲載され、副賞としてラジカセと新譜のLP6枚を頂戴しました(時代が分りますね)。
それがきっかけでもう少し音楽面に重点を置いた「ニュー・ミュージック・マガジン」誌にも別のバンドについて書いた論評を載せていただいたりしました。
渋谷陽一さんとか大貫憲章さんのような評論家を目指した人生のひとコマでした。
そんな夢を見させてくれたきっかけが、このバドカンの1枚目です。
さてこのバンド、なぜかハッピ姿のポール・ロジャースと相まって日本酒のイメージがあるので今夜は熱燗をお作りしましょう。
バッド・カンパニーの曲調
バドカンはフリーに比べて明らかにヒット、とくにアメリカ市場での商業的な成功を狙った曲作りになっています。
とくにミック・ラルフスが中心に作詞作曲を担当した「キャント・ゲット・イナフ(Can't Get Enough)」や「ムーヴィン・オン(Movin' On)」にこの傾向が顕著で、とにかくノリがよくて明るい。
大ヒットした「キャント・ゲット・イナフ」などは、真夜中に恋人未満(多分)の相手の家の前まで押し掛けて「お前がほしい」、早く入れてくれと言っているかなりきわどい内容の歌詞ですが、曲調が軽妙であるためにコンサートで皆が踊る楽しい曲になっています。 フリーのヒット曲「オール・ライト・ナウ」などと比べると能天気といっていい楽しさですね。ただし曲調は明るくても、リズム・セクションが重厚というところにバドカンの特色があります。
一方、ポール・ロジャースが主に作詞作曲を手がけた曲は、やはり歌をじっくり聴かせるブルース調の作品になっている。
全体的にフリーよりも軽いけれど、フリーの延長戦上にいる曲作りなんですね。安心感があります。
この二つの傾向が共存しているのがバドカン1枚目の特徴と言えます。
ポール・ロジャースのボーカル
ポール・ロジャースの天性の歌唱力についてはフリーの『ハイウェイ』の記事でも言及させていただきました。
このアルバムでも、2曲目と3曲目の「ロック・ステディ(Rock Steady)」や「レディ・フォー・ラブ(Ready For Love)」といったブルース系あるいはバラード調の曲で上手さが際立っています。
ちなみに「レディ・フォー・ラブ」はモット・ザ・フープルの『All the Young Dudes』というこれもまた名盤に収められた同曲のカバー。原曲を聴いてみるとギター、ベース、ドラムも悪くないけど、ボーカルのイアン・ハンターがポール・ロジャースに比べるとパワー不足なのが辛い。
4曲目「ドント・レット・ミー・ダウン(Don't Let Me Down)」 (ビートルズとは同名異曲)のような中々うまく行かない恋にじれている様子の歌はロジャースの最も得意とする領域ではないでしょうか。
ポール・ロジャースはこの曲を含む3曲でピアノを演奏。最後の曲「シーガル(Seagull)」ではアコースティック・ギターによる弾き語りを行い多彩な面を見せています。
サイモン・カークのドラム
この人のドラミングには期待を裏切らない安定感があります。
バッド・カンパニーのリズムは重厚で、「キャント・ゲット・イナフ」の1、2、123のカウントの後にドラム、ベース、ギターが一斉にズシーンと入るオープニングや、「バッド・カンパニー」の途中でやはり一斉に入ってくる辺りは目茶苦茶カッコよくてここにバドカン1枚目の魅力が結集しているといっても過言ではありません。なかでもサイモン・カークのお腹にズシンズシンと響いてくるバスドラの音がいい。
ドラムのチューニングについてはよく分りませんが、スネアなど叩くというより全力でひっぱたいている感じです。 フリーの時代もこのひっぱたき感がありましたが、このアルバムではより顕著になっている気がしてそこが魅力というか。
全体的におかずが少なくて黙々と作業に励んでいる印象なのですが、「キャント・ゲット・イナフ」のハイハット、「バッド・カンパニー」の冒頭と中途のシンバル使いが好きです。

ミック・ラルフスのギター
ソロなどを聞くといいギタリストだと思いますが、やはりポール・コゾフの哀しいほど美しいギターと比べてしまいます。優劣というより別物なのですが。
ミック・ラルフスのギターは余白を塗りつぶすような間断のない音でメロディを弾いていて、ところどころ多重録音でツインリードのような効果になっています。
この間を埋めているギターがバドカンのずっしりと詰まった重量感によい意味で寄与しています。
ボズ・バレルのベース
バッド・カンパニーはベーシストが最後まで決まらずに、紙にびっしりと書き出した候補者に片っ端からオーディションをしていったという記事を読みました。
ボズ・バレルの名前はリストの最後に記載されていたが、あまり期待されていなかった。その理由は「他のメンバーがキング・クリムゾンを好きでなかったから」だと。
一応オーディションしてみたら、意外にも一番しっくり来たので選ばれたらしい。
ウィキペディアによればボズ・バレルはキング・クリムゾンに当初ボーカル担当で入ったが、『アイランド』収録前にベーシストとして予定されていたリック・ケンプがドタキャンしたためロバート・フリップとイアン・ウォーレスが当時ギターをちょっと弾けるぐらいのレベルだったボズをベーシストとして特訓して収録に臨んだとのこと。
ベーシストとしての経験年数が少ないにも関わらずセンスのいいベースでバドカンのリズムの要となっています。
「キャント・ゲット・イナフ」のロックン・ロールのベースもいいし、「ムーヴィン・オン」のベースラインは動きが楽しくて魅了されます。
追記
10代で行った2度目のロック・コンサートはバッド・カンパニーでした。
さらに長い年月を経て一番最近行ったロック・コンサートもバッド・カンパニー。2016年のロンドン公演でした。
ギタリストのミック・ラルフスが晩年のグレッグ・レイクに近い肥満体になっていて、一緒に行った友達と「これはちょっとまずいんじゃないの?」と話していたら、
案の定というか公演の当日か翌日に脳卒中で倒れ、命は落とさなかったもののそれ以来ステージには立っていないようです。
ボズは60歳で早くも鬼籍に入っているし、オリジナル・メンバーによるバッド・カンパニーが聴けないのは寂しい限りです。
バッド・カンパニーに限らず70年代に活躍したミュージシャンは70歳前後になっていますが、くれぐれも健康に気をつけて長く音楽を聞かせてほしいと思います。